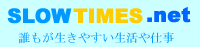□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
スローレポート 『S−Report』 (8/16号)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
関係性の教育学会 地域連携教育に関する研究会です。
◆◆◆ 関係性の教育学会 地域連携教育に関する研究会 ◆◆◆
関係性の教育学会 地域連携教育に関する研究会
日 時:2018年8月31(金) 13:00〜16:30
場 所:大東文化会館 404教室
東武東上線・東武練馬駅徒歩3分
https://goo.gl/maps/uRerxbJubqy
報 告:「地域と教育」(仮) 阿部 英之助(大東文化大学社会学部准教授, 農村社会学)
コメンテーター: 石井 雅章(神田外語大学准教授・言語メディア教育研究センター長, 環境社会学)
進行:長岡 素彦(関係性の教育学会理事)
主 催:関係性の教育学会
問合せ:e-mail ( epajapan@gmail.com )
参加費:無料
サイト https://epajapan.jimdo.com/project-1/2018/
facebook https://www.facebook.com/events/2115354528537033/
趣 旨:
最近、大学の地域連携が盛んになってきています。しかし、大学の都合の地域連携や短期で終了してしまうものも多く、研究・調査の場合も「調査されるという迷惑」(宮本常一)を顧みないものも多いです。
さて、阿部英之助先生(農村社会学)は、和歌山大学、名古屋大学で教育の評価などの研究実践に携わるとともに、2007年度から鶴岡市藤島地域で大学の実習科目のフィールド調査として毎年実施されています。しかし、それは単に社会調査実習にとどまらず、地域づくりへの参加、協力となっています。そして、このたび、大東文化大学社会学部に着任されると、この長期の実習科目のフィールド調査を同大で引き継いで開始されました。
ここから、地域連携教育に関わるものはどうすべきか論議したいと思います。
◆◆◆ おしらせ ◆◆◆
日本ESD学会第1回大会のご案内
第1回大会実行委員会 委員長 宮下 俊也
日本ESD学会第1回大会を下記の要領にて開催いたします。会員の皆様はもとより、学会未加入の方々もお誘いあわせの上、多数のご参加を賜りますようにお願い申し上げます。研究発表並びにワークショップ開催を希望される方は、後述のとおり4月27日(金)までにお知らせください。発表要旨等の原稿執筆要領及び大会参加申し込みは第3報として、5月中旬までに郵送する予定です。皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。
1.主催:日本ESD学会
2.共催:奈良教育大学(予定)
3.後援:一般財団法人奈良県ビジターズビューロー(予定)
4.会場:奈良教育大学(奈良市高畑町)
5.期日:2018年8月18日(土)・19日(日)
6.日程
第1日目 8月18日(土)
12時00分 ~ 13時00分 受付
13時00分 ~ 17時45分 研究発表(口頭発表・ポスター発表)
18時00分 ~ 20時00分 懇親会(大学生協食堂を予定)
第2日目 8月19日(日)
08時30分 ~ 09時00分 受付
09時00分 ~ 11時00分 研究発表(口頭発表)
11時00分 ~ 12時00分 総会
12時00分 ~ 13時30分 ランチタイム
13時30分 ~ 15時30分 ワークショップ
15時40分 ~ 16時20分 ワークショップ報告会・閉会行事
※ ランチタイムに、ブース出展者によるプレゼンを予定しています。
大会参加費
・学会員 500円(資料代)
・非学会員(一般) 事前支払 3,000円 当日支払 3,500円 (資料代含む)
・非学会員(学生) 事前支払・当日支払とも 1,000円 (資料代含む)
・高校生以下 無料
託児施設はございません(あしからずご了承ください)。
観光シーズンですので周辺ホテルの混雑が予想されます。宿泊される場合のご予約は、各自でお早めにお願いします。
未来の学びと持続可能な開発・発展研究会 関西研究会
「PBL 学びの可能性をひらく授業づくり」
持続可能な開発・発展研究会の関西研究会では「PBL 学びの可能性をひらく授 業づくり」の伊藤通子先生の講演と討論を行います。
長年のPBL実践にもとづいてPBLの基礎か らこれからの教育までお話し頂きます。 学校、大学に限らず、地域で問題解決などに取り組む方、ぜひ、PBL (Project Based Learning・Problem Based Learning)を学んでみませんか。
日時 8月20日(月)12時30分-16時
場所 大阪国際大学 守口キャンパス1号館501教室
http://www.oiu.ac.jp/access/
主催 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会
内容
挨拶 未来の学びと持続可能な開発・発展研究会 共同代表 田中優(大阪国際大学教授)
基調講演 「PBL 学びの可能性をひらく授業づくり」
東京都市大学 教育開発機構准教授 伊藤通子 (未来の学びと持続可能な開発・発展研究会)
問題提起 兵庫県立大学教授 畑正夫 (未来の学びと持続可能な開発・発展研究会)
伊藤通子先生(いとうみちこ)
35年間、富山高等専門学校にて、ESD(持続可能な開発の ための教育)、環境安全教育、ものづくり教育、倫理等を、 専門の座学や実験・実習科目と統合する「Problem-Based Learning=現実問題に基づく学習」の授業づくりに取り組み、 様々な教育プログラムを開発してきた。
その後、東京大学大 学院 新領域創成科学研究科 特任研究員、NPO法人持続可能な開発のための教育推進会議(ESD-J)事務局長を経て、2017 年10月より現職。
主催団体
未来の学びと持続可能な開発・発展研究会は、異なる専門 分野(社会学、法律学、環境心理学、行政、教育等)の実践的な 研究者の分野横断的・越境的研究・実践団体です。 主なテーマは「持続可能な開発・発展・SDGs持続可能な開 発目標」と「教育・PBL (Project Based Learning・ Problem Based Learning)・ESD(Education for Sustainable Development)」の実践と研究です。
参加費無料・参加者は必ずご連絡ください。
・未来の学びと持続可能な開発・発展研究会事務局(東京)
日本建築学会 環境心理小委員会人類学的アプローチWG 拡大研究会
「まちづくりのエスノグラフィ:筑波山麓地域の開発プロジェクト
を対象として」
講演者:早川公先生(仁愛大学 人間学部 コミュニケーション学科
専任講師・人類学者)
概要:
「まちづくり」といった建築的な興味の対象に「人類学的」なア
プローチをした実践の中で、どんな面白さや難しさが体験されたの
かを伺い、人類学的アプローチの展望と限界について参加者ともど
も議論します。
日時:2018年9月10日 (月)14:00~16:15
※研究会終了後に懇親会を予定(希望者のみ)
場所:建築会館 305会議室
東京都港区芝5丁目26番20号
https://www.aij.or.jp/jpn/guide/map.htm
定員:26名(先着順)
参加費:無料
コーディネーター:村松 陸雄(武蔵野大学)
主催:社団法人日本建築学会 環境心理小委員会人類学的アプロー
チWG
共催:未来の学びと持続可能な発展・開発研究会(みがくSD研)
未来の先生展2018
学生と共に学ぶSDGsワークショップ
未来の先生展2018で未来の学びと持続可能な開発・発展研究会は学生と「学生と共に学ぶSDGsワークショップ」を行います。
日程は、主催者事務局から公表され次第お知らせします。
▼特徴
持続可能な開発目標の考え方やそれぞれの立場から目指すべきことについて、学生を交えたワークを通じて理解するワークショップです。SDGsについての単なる講義や与えられたワークをだたこなすのではなく、SDGsをテーマにしたワーク作りに関わった学生たちと共におこないます。
▼詳細
2015年9月に国連が採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において示された2016年から2030年までの国際目標であるSDGs(Sustainable Development Goals)を、グループワークと成果物の共有をつうじて、体験的に理解をすることを目的としたワークショップです。
SDGsでは貧困や環境など17の目標が提示されていますが、各目標はそれぞれ密接に関連しています。このワークショプでは、SDGsの目標をバラバラに捉えるのではなく、「目標どうしの関連性」について、わかりやすく理解することを目指します。また、世界中の人びとがゆたかで幸せに生き続けることができる「持続可能性」についての感覚を、ワークを通じてお互いに共有していきます。
今回のワークショップは、日頃からSDGsの実践的研究に取り組む大学教員・NPO・行政・環境団体の関係者に加えて、現役の学生たちにも事前のワークづくりに関わってもらい、その学生たちと一緒になってグループワークをおこなう「多世代交流型ワークショップ」をおこないます。
参加者の皆さんには、たんにSDGsについての知識を得てもらうのではなく、SDGsの考え方や意義を伝える次の担い手としての経験と感性を得られるワークショップにしていきます。
持続可能な社会の実現に向けて、立場や世代を超えた学びの場を一緒に体験しましょう。
▼対象
小学生(高学年)から大学生、社会人、保護者まで
▼主催団体・登壇者
未来の学びと持続可能な開発・発展研究会(みがくSD研)
未来の学びと持続可能な開発・発展研究会は、異なる専門分野(社会学、法律学、環境心理学、行政、教育等)の実践的な研究者の分野横断的・越境的研究・実践団体です。
主なテーマは「持続可能な開発・発展・SDGs持続可能な開発目標」と「教育・PBL (Project Based Learning・Problem Based Learning)・ESD(Education for Sustainable Development)」の実践と研究です。未来の学びと持続可能な開発・発展研究会は自主研究だけでなく、学会や地域団体、学校、自治体、企業、CSO(NGO・NPO)などのマルチセクターと協働し、研究と実践を行っています。
https://sdgspbl.jimdo.com/
▼主催者からのメッセージ
未来の学びは、異なる立場や世代のひとたちが一緒に学び合うことから始まります。
主催者サイト
未来の先生展2018 http://www.mirai-sensei.or
〓〓 SITE 更新情報 〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
以下も継続します。
Sustainablefuture.jp
http://www.sustainablefuture.jp
大切なことを伝えよう
市民メディアslowtimes.net
http://slowtimes.net/
想いをカタチに
ソーシャルプロデュースネッ
 Slowtimes.net
Slowtimes.net