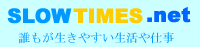ESD-J全国ミーティング2013
1日
6月15、16日に岡山市でESD-J全国ミーティング2013in岡山「未来へつなぐ」を現場で学ぶ~2014年のESDユネスコ世界会議と2015年以降のESDの推進に向けて~」(主催 ESDJ「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議 共催 岡山市)で開かれ、1日目123名で、2日目のみの参加者とあわせると141名の参加があった。
「今年のESD-J全国ミーティングは、「ESDの視点を持ったコーディネーター育成とそのネットワークづくり」をテーマに、国内でもっともESDが盛り上がっている場所のひとつ、岡山市で開催します。
岡山市は2005年に、学校や市民団体、企業、行政など、立場や分野の違う人たちが集まりESD を推進する「岡山ESDプロジェクト」を立ち上げました。市内に37 ある公民館を地域のESD 推進拠点と位置づけ、それぞれの地域でESD を進めています。
今回は、これらの公民館の活動をコーディネートしている「つなぐ人」や、全国各地のキーパーソンとともに、それぞれのテーマごとにESDコーディネーターの果たす役割やコーディネートのコツなどについて、参加者のみなさんとともに学びあっていきたいと考えています。
ESDとはヨハネスブルグサミットにおいて日本が提唱し実現した「国連持続可能な開発のための教育の10年」は、2005年から2014年迄行われる「持続可能な開発のための教育=Education for Sustainable Development」のことである。
これは社会・環境・経済・文化の視点から、人類が直面する様々な課題に取り組み、公正で豊かな未来を創る「持続可能な開発」を実現する力を、世界各地に生きる私たちひとり一人が学び育むことを目指している。

主催者挨拶の後、「現場での ESD 実践拡大に向けて~2014年に向けた文部科学省と環境省の取組を聞く~」が行われた。
文部科学省国際統括官付国際交渉分析官の岩本渉氏が「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議について」述べた。
教育振基本興計画にも位置づけられているESD、及び、ESDに関するユネスコ世界会議について述べ、2014年以降のESDの推進としてESDネットワーク(ユネスコスクール)、ESDの教育内容への波及効果について語った。

環境省環境教育推進室室長の宮澤俊輔氏が「環境省におけるESDの取組状況等について」述べた。
ESDに関するユネスコ世界会議とこれまでの環境省におけるESDの取組状況等について語った。

同代表理事の阿部治氏と両省で、これまでの成果を踏まえて2015年以降のESD推進について論議した。
ここでは両省とも2015年以降のESD推進に前向きな意見を述べた。

「ESDと震災~災害教育という考え方」として一般社団法人RQ災害教育センター代表の広瀬敏通氏の講演が行われた。
同氏はRQ災害救援センターを設立し、実際に災害支援をしてきた経験から災害の教育的効果について実例から語り、災害現場が学びの場になっていることを『災害教育』と呼び、防災教育の弱点(事前・事後でない事中での学び)を災害教育を埋めることなどを述べた。
被災地で生まれる教育的効果は副次的効果だが重要であるが、災害現場にいった人にしか伝わらない暗黙知ともいわれるものが、学びになり、災害時には「自己中」人間だけでは人間関係が維持できないのでいざとなったら利他的になる。つまり、「災害が、利他を生む」という。

「未来へつなぐ人(ESDコーディネーター)育成プロジェクトについて」では、多様な人々、多文化・生物多様性をつなぐESDコーディネーターのあり方と取組みをESDJ「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議が発表し、会場と論議した。
また、環境、国際、まちづくり、福祉などのいろいろな分野をそれぞれの分野のそういうコーディネーターが協力して行うESDコーディネーションのためのビジュアル教材を公開した。

「岡山市におけるESD ESDをすすめるしくみと多彩な活動」として岡山市ESD世界会議推進局の原明子氏が自らの体験を交えてESDはつながりを気付くことであると述べた。
また、「多様な人々のゆるやかなつながりにより持続可能な社会づくりを目指す」岡山市におけるESDの目標・仕組みについて語り、地区・公民館などの実践と岡山市でのユネスコ世界会議について語った。
 Slowtimes.net
Slowtimes.net