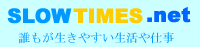「彩の国NPO・大学ネットワーク」の全体会
(年度報告会)
5月25日、「彩の国NPO・大学ネットワーク」の全体会(年度報告会)がさいたま市で開かれた。
この団体の設立の経緯・趣旨は下記の通り。
「平成19年度から3年間にわたり開催された「NPO・大学シンポジウム」の実行委員会が提案した「NPO・大学シンポジウム 埼玉宣言」を受け、この宣言の趣旨に賛同するNPOや大学、企業、行政などが、大学生の学びの場の充実やNPOと大学の協働の更なる促進に向けて共通課題の解決を図るため、このたび「彩の国NPO・大学ネットワーク」を設立します。」
埼玉大学教授の松本正生氏の挨拶の後に 、事例発表が行われた。

事例1として芝浦工業大学システム理工学部三浦研究室「安全・健康の街づくりに向けた自治会との協働事例「住環境プロジェクト」」では同大の三浦研究室の学生が発表した。
三浦研究室では、「ご自身のまちを愛されている方々に少しでも役に立ちたい」という想いでも関東各地で住快環プロジェクトを行っている。
この住快環プロジェクトは、住民と三浦研究室が、話し合いからアンケート調査から始め、サポートして実測調査も行い、地域の改善を支援している。
実際に、上尾市の陣屋町内会の会長が住快環プロジェクトの事例を語った。 同町内会は約700世帯加入してるが、従来より住民が夜間に道路を利用する際不安に感じていたが、要望だけではなかなか街灯の設置はされなかった。 これに対して、三浦研究室が夜間の明るさの科学的・都市計画的調査を行うことで、上尾市役所に合理的な調査結果の報告し、まちが明るくなった。
また、これらの活動をすすめて町内の防犯ボランティア活動を活発化して、県内のモデル事例になったという。
芝浦工業大学システム理工学部三浦研究室http://www.mmlab.se.shibaura-it.ac.jp/

事例2として獨協大学経済学部高松ゼミ「共助の取組発信(吾野宿のまちづくり等の広報)」では同大の高松ゼミの学生が発表した。
高松ゼミは、県内各地での地域活性化に向けた活動や埼玉県ふるさと支援隊などの活動を行っている。
そのうち、今回は「高齢化や過疎化の進行等により、農林業や地域活動の維持が困難な状況にある埼玉県内の中山間地域」への大学・学生の力を活かす埼玉県ふるさと支援隊として飯能市吾野地区での活動の報告が行われた。
高松ゼミは、吾野地区の生活を学生の学びの場にしながら、「大学生の若い視点から同地区の人、自然、資源を生かした活用方策による協働活動を実施することを活動の目的としています。現在、耕作放棄地の再生作業や特産品開発を通じて住民との交流を図るとともに、地域資源マップの作成により都市住民との交流を促進する活動を展開中」である。
獨協大学経済学部高松ゼミ http://www2.dokkyo.ac.jp/~msemi011/
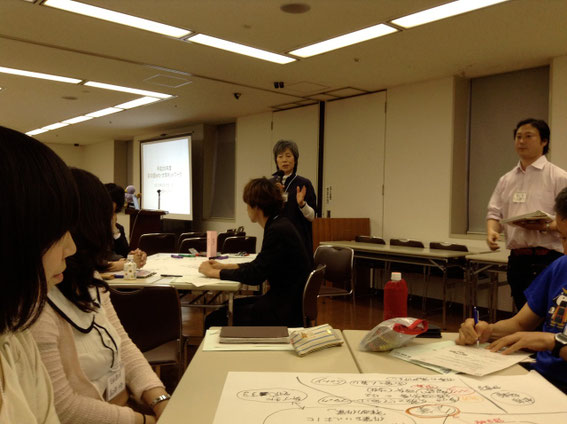
その後、「平成25年度以降の運営方針及び事務局の件」として、彩の国NPO・大学ネットワークの事務局を件からさいたまNPOセンターへの移管と、25年度事業としてNPOインターンシップを加速化させるためにインターンシップ部会を設けることなどが提案され、承認された。
その後、「NPO・大学の連携のヒント~インターンシップ~」をテーマにワールドカフェが行われ、インターンの受入れ、プログラムの課題、NPOと大学の連携によるインターンシップの可能性などが話し合われた。
最後のまとめでは、私たちの行っている地域起業・NPOインターンシップの紹介も行うことができた。

 Slowtimes.net
Slowtimes.net