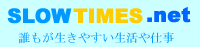<3度目の春> 住宅再建 人々の孤立防ぐ復興を
「漠然とした不安」。NPO法人くらしのサポーターズの吉田直美副理事長は、被災地の空気をこう表現する。宮古市に開いた「あすからの暮らし相談室」に寄せられた多くの声を聞いた印象だ。
「災害公営住宅にいつ入居できるのか」「義援金や支援金が目減りしていく」「あと何年生きられるのか不安」「それまでに仮設住宅を出られるのか」-。
見えてくるのは、数年後の自分がイメージできず、1人で悩む被災者の姿だ。相談する相手もなく、孤立している人が目立つという。岩手日報社が行ったアンケートでも、今後の不安は「住宅の確保」「自分や家族の体調」が抜きんでて多かった。
将来が不透明な理由の一つは、生活の基盤となる住宅建設の遅れだ。県内で完成した災害公営住宅はわずか0・8%。高台移転のための防災集団移転促進事業、区画整理事業も足踏みしている。
東日本大震災の発生から今日で丸2年。被災した誰にも同じ時間が過ぎたが、自力で生活を切り開けない人々は、よりつらい日々を積み重ねてきた。
「これから先が一番しんどい」。京都大防災研究所の牧紀男准教授は今月初め、仙台市で開かれた日本建築学会の勉強会で懸念を語った。これまでの2年間は、被災から避難所、そして仮設へと苦しい中でも動きがあった。
しかし、この先はなかなか前に進まない。阪神大震災でも同じような経験をした。仮設がなくなるまでには5年かかった。頑張っても進まない中で、無力感が生まれやすい。仮設に取り残される人の焦りも心配だ。
その焦りを増幅しないためにも、行政が設ける「時間の壁」は柔軟であるべきだ。仮設の入居期間、被災者生活再建支援制度の支援金申請期限は1年刻みに延長されてはいるが、力が弱い人々に配慮したまなざしがほしい。
そして、住まいを得ることが復興のゴールではない。災害公営住宅には高齢者の入居が多くなると予想される。今後も医療・介護のニーズや生活困窮などの悩みは尽きないが、また孤立していく心配はないのだろうか。
NPO法人くらしのサポーターズの吉田さんが訴えるのは、寄り添い型・伴走型の生活支援。「行政の数々の窓口は開設されているが、縦割りでは複雑な悩みに応えきれない」と指摘する。
被災地はもともと、少子高齢化が進行していた地域。いずれは日本のどこでも直面する社会だ。高齢者はもちろん、誰にも居場所があり、それぞれが生きがいを感じられる。そんな古里の再生をもう一度誓おう。
(村井康典)
 Slowtimes.net
Slowtimes.net