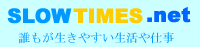心を痛めている。
……という書き出しを読んだ瞬間に
「なんだこの偽善者は」
と身構えるタイプの読者がいる。
ながらく原稿を書く仕事をしてきて、最近、つくづく感じるのは、若い読者のなかに、情緒的な言い回しを嫌う人々が増えていることだ。
彼らが嫌う物言いは、「心を痛める」だけではない。 「寄り添う」「向き合う」「気遣う」「ふれあい」「おもいやり」「きずな」といったあたりの、手ぬるい印象のやまとことばは、おおむね評判が良くない。かえって反発を招く。
彼らの気持ちは、私にも、半分ぐらいまでは理解できる。
この国のマスメディアでは、論争的な問題を語るに当たって、あえて情緒的な言葉を使うことで対立点を曖昧にするみたいなレトリックを駆使する人々が高い地位を占めることになっている。彼らは、論点を心情の次元に分解することで、あらゆる問題を日曜版に移動させようとしている。
若い読者は、そういう姿勢の背後にある卑怯さを見逃さない。 リテラシーとも読解力とも違う、不思議な能力だ。
なので、冒頭の一行目については、思っている通りの言葉で言い直してみることにする。 私は、心を痛めているのではない。私は、アタマに来ている。 あるいは「うんざりしている」の方がいまの気持ちに近いかもしれない。 私はうんざりしている。
ついこの前の日曜日(2月17日)に、新大久保で「不逞鮮人追放!!韓流撲滅デモ」と銘打たれたデモが開催された。
2月に入ってから、新大久保での嫌韓デモは3回目になる。 これ以上の詳細については、各自「新大久保」「デモ」「嫌韓」ぐらいのキーワードでググってみてほしい。色々と動画やブログがヒットするはずだ。
デモの映像を見ると、たった10年前の常識で考えても、到底考えられなかったことが、いま現実に起こっていることに驚かされる。それほど、社会の変化は素早い。私の常識はまったく通用しない。
ここで引用できない言葉を記したプラカードが、東京の街中に掲げられて実在すること自体、たぶん、10年前の日本人は信じられないはずだ。 が、現実として、そのプラカードを振りかざす人間がいて、その彼は公道を闊歩している。
戦後常識からしても、国際標準からしても、あり得ない出来事なのだが、彼らは誰にもとがめられない。 列に連なっている人々は、これまた、とてもここでは引用できないシュプレヒコールを繰り返している。 引用できない以上、論評のしようがありません。
デモが起きた翌日(2月18日)の夜、NHK広報局のツイッターアカウントである@NHK_PRが以下のようなツイートを書き込んだ。
 Slowtimes.net
Slowtimes.net