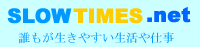□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
スローレポート 『S−Report』 (12/27号)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
◆◆◆ 「ESDと復興 岩手 災害と学校教育」 ◆◆◆
山田町セッション・大槌町セッション
「ESDと復興 岩手 災害と学校教育」の山田町セッション・大槌町セッションが行われた。
http://www.slowtimes.net/2012/11/24/220121124/ http://www.slowtimes.net/2012/11/25/20121125/
11月24日、「ESDと復興 岩手 災害と学校教育」の山田町セッション(主催 ESD学校教育研究会、岩手大学教育学部梶原昌五 協賛 岩手大学社会学教室麦倉研究室)が行われた。
岩手県内の津波被災地で、被災した学校がどのような状態であったか、また、学校が今後教育すべきことは何かを一緒に考えます。
視点はESDです。将来の子どもたちに、どのような街に住んで、どのような生活をして欲しいのか。私たちの今を考えながら、未来のこの街を一緒に考えます。そこから、私 たちが目指すべき「持続可能な街に住むための教育」が導き出されると思います。(趣旨)
岩手県山田町の船越小学校の前の浜。
穏やかな海に、しっかりした防潮堤。
その防潮堤の向こうの高台に船越小学校があった。
震災のあったあの日、
とてつもなく大きな地震がきて、
船越小学校にいた児童は定められた手順に従ってこの校庭に出た。
地震が鎮まるまで、ここで待機のはずだった。
海を良く知っている校務員のひとが裏山に逃げなくてはといった。
校長もそれを支持して
この急な裏山を全員で必死で登った。
津波はしっかりした防潮堤をあっさり超えた。
さっきまでいた小学校の校庭は津波はのみ込まれた。
実際に登って驚くほどの急斜面を、
1年背から6年生までひとりのけがも無く駆け上がった。
頂上についたがそこは小さな空間しかない。
そこで励まし合いながら潮の引くのを待ちつづける。
何の情報もないまま、夕方まで待ち続けて
何回も下の様子を見に行って
学校よりはるかに高い位置の3軒の家のあるところまでもどった。
学校は海の下。
勇気のある若者が津波を顧みず、我が子と小学校を心配してかけつけた。
100名以上の児童と教職員、
そして、逃げてきた地域の人が この3軒の家で一晩を過ごした。
次の日、若者の知らせを聞いた父兄をはじめとした人々がこどもたちを迎えにきた。
奇跡ではないが。奇跡的だ。
こどもたちの力が、ひとりひとりの力が何一つ、欠けていてもできなかっただろう。
その後、山田町の船越公民館で意見交換会を行った。
まず、同町の震災・津波被害と現況について説明があった。
漁師の方においで頂き、復興しない漁業について伺った。
まだ、漁港の整備がすすんでおらず、地元で水揚げができないこともあり再開が困難である。 また、船と漁業用具が流され、新たにどちらかが確保できても片方だけでは再開できず、政府の補助も新規漁業就業者を優先する政策のために補助の順番が回ってこない。
養殖についても、政府の支援の仕組みはグループ化による漁獲高を担保した先行貸し付けであって問題も多い。
そして、このように親に仕事が無いと、こどもにも希望も無く、元気が無い。
11月25日、「ESDと復興 岩手 災害と学校教育」の大槌町セッション(主催 ESD学校教育研究会、岩手大学教育学部梶原昌五 協賛 岩手大学社会学教室麦倉研究室)が行われた。
岩手県内の津波被災地で、被災した学校がどのような状態であったか、また、学校が今後教育すべきことは何かを一緒に考えます。 視点はESDです。将来の子どもたちに、どのような街に住んで、どのような生活をして欲しいのか。私たちの今を考えながら、未来のこの街を一緒に考えます。そこから、私 たちが目指すべき「持続可能な街に住むための教育」が導き出されると思います。(趣旨)
岩手県大槌町のプレハブ校舎。
昔、プレハブ校舎に通ったことがある。
夏は暑く、冬は寒い。 震災から1年半以上立った。
このプレハブ校舎と一つの校庭に 大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校 大槌中学校が入っている
大槌の私立のみどり幼稚園
外見はなんともない。
それもそのばず、
園児の安全ために新築したばかり。
津波は柱までやってきた。 園長先生は、普段から園児とともに備え、
父兄にはていねいに説明をしてた。 津波がやってきた日にも
バスで避難することができた。 奇跡ではないが。奇跡的だ。
こどもたちの力が、ひとりひとりの力が何一つ、欠けていてもできなかっただろう。
その後、大槌町の大槌高校同窓会館で意見交換会を行った。
まず、同町の震災・津波被害と現況について説明の後、大槌のみどり幼稚園、山田町、船越小、大槌中、大槌高、南三陸町伊里前小などの父兄、教員、事務職員、校務員などの方々が集まり話し合った。 学校から津波から逃げた時の状況、判断、マニュアル、制度、プログラムなどについて語られ、全体で論議した。
◆◆◆ ご案内 ◆◆◆
関東ESD学びあいフォーラム2013 ESDの視点をプラス
身近な活動を持続可能な地域づくりにつなげよう
【日時】 2013年1月26日(土)10:00~17:00
【会場】 ガールスカウト会館
(→http://www.girlscout.or.jp/contents/wp-content/themes/girlscout/images/kaikan_map.pdf)
地域には、さまざまな課題を抱えた人がいます。日本語が不自由で生活に困る、農業の後継者がいない、安心してのびのび遊べる場所がない、身近な環境を守りたい・・・・。
そんな課題を解決しようと始まった取り組みは、時に地域に広がり、多様な人をつなぎ、かかわった人たちを元気にしていきます。そんな活動に共通するポイントはなんでしょうか?
本フォーラムは、活動の実践者や地域のコーディネーターの皆さまと、地域によくみられる課題解決の取り組みを、ESDの視点でブラッシュアップするワークを通して、それぞれの活動を持続可能な地域づくりや人づくりにつなげていくポイントを共有することを目指します。
*ESD:持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)
●こんなNGO・企業・学校・つなぐ人にお勧めです 環境各地域のESDに関心を持つ市民活動実践者、教員、企業人、行政職員 市民参加やボランティアのコーディネーターなど
【プログラム内容】
10:00 全体会 講演「持続可能な地域をつくるESDの視点とは」 森 良(ESD-J理事)
11:15 分科会 「身近な課題に、ESD的に取り組むには?」
①環境教育をいかして多文化共生をすすめたい 太田祥一氏(群馬県生涯学習課)
②地域とつながりをつくりたい 菊地敦子氏(workshop”reco”) ③地域の環境を大切にした農業を守りたい 加藤大吾氏(都留環境フォーラム)
④貧困で未来を描けない子どもをなんとかしたい 栗林知絵子氏(豊島WAKU WAKUネット)
(12:00~13:00昼食・休憩)
14:45 全体会 「ESD化するための視点を抽出し共有しよう」
1)各分科会からの発表
2)ふりかえり、グループワーク&全体セッション
16:30 情報共有:+ESDプロジェクトのご紹介
関東でのESDコーディネーター研修のご紹介
17:00 終了
☆申し込みはこちら(→https://goo.gl/h5tuj)sw
〓〓 SITE 更新情報 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
スロータイムス★メールマガジン http://www.slowtimes.net/slowtimes-1/
大切なことを伝えよう 市民メディアslowtimes.net http://slowtimes.net/
想いをカタチに ソーシャルプロデュースネット http://socialproduce.net/
こどもと地球の平和的未来をつくる教育 ESD http://esd.weblogs.jp/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
スローレポート『S−Report』●ご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
●掲載された記事を許可なく使用することはご遠慮ください。●ご紹介または転載等のご相談は下記までお願いします。●掲載している情報は各人の責任においてご利用ください。●この情報レポートが不要の場合はご連絡または、下記でお願いします。Slowtimes.net http://slowtimes.net fq@slowtimes.net
 Slowtimes.net
Slowtimes.net