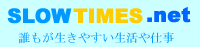NGO・企業・地域と学校の連携で豊かな学びを生み出そう
基礎編 学校のニーズを把握し、学習活動を提案する
平成24年度環境保全戦略講座
11月10日、「NGO・企業・地域と学校の連携で豊かな学びを生み出そう 基礎編 学校のニーズを把握し、学習活動を提案する」(平成24年度環境保全戦略講座 環境教育分野)が東京青山で行われた。
(主催:独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部 企画・協力 :認定NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議)

「豊かな環境学習を学校で展開したい
そんな思いを持つ学校の先生や環境NGO、企業、地域の人々はたくさんいます。でも、いざ外部講師が学校で授業を展開しようとすると、学校に受け入れられなかったり、授業がうまくいかなかったり・・・。でもそれには理由があります。
環境問題をよく知っているだけでは、学校で子どもたちの学習の場を作れるとは限りません。
この講座では、NPO、企業、地域の人々などの外部講 師予備軍と、学校、そしてそれらをつないでいくコーディネーターの皆さんが一緒になって、子どもたちにどのような学びを生み出そうとしているのか、そのためには何が大切かについて学びあい、よりよい連携を生み出す力をつけたいと思います。」
環境再生保全機構の趣旨説明と持続可能な開発のための教育の10年推進会議による進行の説明が行われネアイスブレイクで自己紹介が行われた。

基調講演「地域・社会に学校を開く意義ー学校はこんなことを期待している」として多摩市立東愛宕中学校校長の冨田広氏が三宅島と多摩の中学校での体験から学校と地域のあり方を述べた。
2000年の噴火によって三宅島の全島民島外避難から5年後の帰島に際して中学校の校長に請われた冨田氏は、島の復興には学校と生徒の力が必要とされると考え、学校による復興を実行した。
生徒がボランティアたちと協力して火山灰の除去を行うことから始まり、総合的学習の時間、職場体験などで生徒が学校から出て行くことで、地域にこどもの声が聞こえ、島のひとたちが元気になったという。
一方、5年間島を離れた生徒たちは「島の子」ではなくなり、島の生活になじめなかったり、魚もさばけないという状況であり、それに対してシーカヤックで海に親しむことから始まり、魚のさばき方講座などの体験学習を行ったという。
その後、多摩市の中学校に転任となった同氏は、困難な状況にある中学校を挨拶をすることからはじめ、少しずつ変えて行く。
そして、緑のカーテンでてきたゴーヤを地域の高齢者に贈ることから始じめ、ゴーヤの縁で地域に入り、生徒たちも地域の大人から評価されるようになって変わったという。
同氏は、地域・社会に学校を開く意義は「人は人によって磨かれ光る」のだから、生徒が地域の人に育ててもらえば成長するといことだと述べた。
そして、生徒も学校も教員も、地域も「行動によって変わる」と語った。

次に講義が行われた。
「学校とつながるための視点」として足立区立梅島小学校副校長の石田好広氏は、学校の立場から学校との連携について述べた。
石田氏は、学校や教員のおかれている状況を統計などにもとづていて客観的に説明し、学校との連携を阻む4つの壁として「忙しさの壁」「組織の壁」「意識の壁」「時間の壁」について述べた。
また、学校との連携の成功事例を語り、学校とつながるにはWIM-WINの関係、優れたプログラム・教材、学校との連携の実績が必要と述べた。

「NGOの立場から」としてNPO法人川口市民環境会議代表理事の浅羽理恵氏は、NGOの立場から学校との連携について述べた。
川口市民環境会議は、地球温暖化防止のための新しい方式である「エコライフDAY」を開発し学校から地域に広げ、学校でも多くの環境の出前授業やこども主体の環境フォーラムを行っている。
浅羽氏は、その体験から学校へのアプローチ、授業案のつくり方、先生との連携の工夫などを具体的に述べ、授業づくりについて自ら作成した「ノウハウ集 環境出前授業」にそって実践的に語った。
「出会いと挑戦の教育 市民参加の教育づくり」としてNPO法人アスクネット代表理事の白上昌子氏は教育コーディネーターの立場から学校との連携について述べた。
アスクネットは愛知県を中心に学校とまちをつないでいく教育の専門家「教育コーディネーター」として「人のつながりのなかで、人は成長し、人の成長がまちを元気にしていく。そんな「学び合いのコミュニティ」を創りだす」新しい教育モデル「市民参加の教育づくり」を行っている
白上氏は、企業と連携したアイシン環境教育プログラムについて述べ、コーディネーターとして気をつけていることや実践方法を語った。

これを受けて参加者がグループに分かれて、講演や講義から学んだことを論議した。
その後、実習として参加者がグループに分かれて授業案づくりを行った。参加者が持ちよった授業案を検討し、別の参加者がアドバイスを行って、それを発表した。
 Slowtimes.net
Slowtimes.net